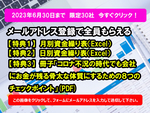定 休 日:年 中 無 休
会計を学びたいが、簿記のテキストを見ただけで挫折感がでる社長の悩みにお答えします~社長は決して簿記の仕訳から入ってはいけません~

目次
1.会計を学びたい社長が悩む4つのこと
2.社長が学ぶ会計の正しい学び方の順序
3.まとめ
1.会計を学びたい社長が悩む4つのこと
会計を学びたい社長のよくある悩みは以下の4つです。
①本屋に行ってもどれから勉強したらよいかわからない
②簡単・入門と書いてあってもどれも難しい
③簿記入門のテキストを買っても、最初の仕訳でつまずく
④簿記学校または通信講座を申し込んでも、継続できるか不安
本屋に行くと、たくさん会計の入門書がおいてあります。
どれも簡単とか入門とか書かれています。
しかしいざ買ってみて家に帰って読んでみると最初の10ページ、20ページでつまずきます。
会計は言葉が難しいからです。
はじめての人は、まず言葉の意味でつまずきます。
おすすめはマンガで書いてある超入門書をとりあえず、1冊読み切ることです。
②簡単・入門とかいてあってもどれも難しい
「簡単・入門」と、どの本も書いてあります。
これは著者のほとんどが公認会計士・税理士・会計学者であって、そのような専門家から見た場合に、本当にその程度は、簡単・入門レベルだと思っているからです。
このように、ちまたにある簿記会計の入門書のほとんどは、「専門家から見た場合の簡単なレベル」なのだと覚えておいてください。
会計は一見簡単なようで、実は奥がめちゃくちゃ深いのです。私も会計の深みにはまって、プロレベルになるまで、勉強~実務含めてざっと15年は時を費やしてしまいました。
それでももちろん完璧でありません。
制度が日進月歩で変化していきますので、会計のプロはどんどん新しいことを取り入れていかなければならないのです。
少しイメージが湧きましたでしょうか?
そのようなプロから見ての「簡単・入門」なのです。
③簿記入門のテキストを買っても仕訳でつまずく
例えば、簿記入門テキストとして一般的なのが「簿記3級のテキスト」です。
こえは基本的に講義と一体になっているものですので、これを家で1人でマスターするのは、よほどの意思の強い方や、本当にこの分野に向いている方でないと難しいです。
私も遠い昔の学生時代ですが、大学の簿記の授業がわからなくて、市販の簿記3級のテキストを買いましたが、とても最後まで読む力はありませんでした。
もっとも最近は図や絵が多くなって、読みやすいテキストも多く出てきています。
おすすめはマンガが多く入っているテキストです。
④簿記学校または通信講座を申し込んでも、継続できるか不安
簿記3級検定のクラスを申し込むと、1回2時間~3時間の講義が15回くらいあって、最後の5回くらいが答練と模擬試験となります。正直、授業スピードがかなり速くてきついと思います。
ポイントは、
①最初の1回~3回の授業についていけるのか?
②わからない場合、講師にわかるようになるまで質問できるか?
です。
講師は質問に来ない人までは対応できません。
通学だと、ついて行けなくなると足が遠くなります。
その点、通信だと何回も繰り返し視聴できるので、ついて行けなくても気分が憂鬱になりにくいメリットはあります。
しかし、通信だと怠けます。
もし怠けない自信があれば、時間効率的には通信がおすすめです。
しかし、講師に質問できる環境では通学が断然優れています。
このようにどちらもメリット・デメリットがあります。
いずれにしても、最後までやめないで受講できるか?
意志力の問題となります。
しかし時間効率の観点・費用対効果の観点からは、本でマスターするよりは効率的です。
2.社長が学ぶ会計の正しい学び方の順序
社長が学ぶ会計には正しい学びかたの順序があります。
社長が会計の知識を習得するにあたって、一番大事な目的は「経理ができる」「税金の計算ができる」ことではなくて、「会計を経営に役立てる」ことです。
会社を倒産させる中小企業社長の99%は会計の知識がありません。
99%が 言い過ぎでしたら、95%と言いかえましょうか。どちらにしてもそれぐらいの高いレベルです。
これは私が過去2000人以上の中小企業社長と会った結果、その体験から言っています。
信じない方は信じなくて結構ですが、事実だからしかたありません。
現在日本で事業している事業者約350万社、その内法人が200万社あると仮定すると、法人だけにしぼって200万社だけを見ても、その内80%の社長は少なくとも会計を勉強していません。あるいは過去にかじったことがあるかもしれませんが、現在のところ現実には経営に使えてないのです。
200万社うちの80%というと160万社です。となると残りは20%の40万社です。
社員5人以下(製造業は20人以下)の小規模企業を除いた中小企業の数が約50万社ですから、何となく説得力ある数字ですね。
社長が会計を勉強しないと小規模企業から脱せずに、大企業はもちろん、中小企業にもなれないということなのです。
しかも倒産するリスクが非常に高いのです。
なぜこんなことが言えるのかといいますと、会社を倒産させる社長はB/S(貸借対照表)P/L(損益計算書)を見ていません。見ていたとしてもその意味が理解できていません。また、会社を成長させることができない社長もB/S、P/Lの意味が理解できていません。ここでB/SとP/Lというものは、会社が会計処理をおこなって最終的にまとめた報告書です。
会計の目的はB/S、P/Lをつくることです。社長はこのB/S P/Lを見て経営判断するのです。ですから社長は会計を勉強するにあたって、このB/S P/Lの意味の理解から入るのが正しいのです。
3.まとめ
今回のテーマのまとめです。
本屋にある多くの簿記会計の本は、経理をする人を養成するための本です。ですからほとんどは、仕訳から書いています。もちろん「仕訳から勉強したい!」という社長は一度チャレンジしてみてください。
それは
①わかりやすいマンガの本から入る。
②本格的に学ぶなら通学か通信で簿記を学ぶ。
この2点について書きました。
しかし、社長が会計を勉強する正しい順序は、経理を目指す人とは違うのです。
社長は
①B/S(貸借対照表)、P/L(損益計算書)の読み方をまず勉強する。
②次にこのB/S、P/Lが、どのようなプロセスを経て作成されているかを勉強する。
この順序で勉強するのがもっとも効果的かつ有効な方法です。
繰り返しますと
①読み方→②仕訳
この順序で勉強するのが、社長が会計を勉強する正しい方法です。
しかし、残念ながらこの方法で学んでいる人は世の中にほとんどいません。
もし社長、ベンチャー起業家の方、これから起業しようと思っている方で「会社を倒産させずに、成功させたい」と思わる方はぜひ私と一緒に今後学んでいきましょう。
ではまた次回お会いしましょう。