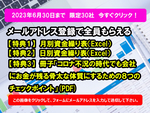定 休 日:年 中 無 休
社長が考えている会計についての誤解の原因はコレです~実は会計には3種類あるのです~

会計を勉強するのに普通は仕訳から入りますが、のぶ@ブログでは経理マンではなく、中小企業社長、ベンチャー起業家を対象にしているため、仕訳から入りません。
まずは決算書の構造理解からお伝えいたします。
多くの方は、簿記3級の教科書の最初でつまづきます。
簿記3級は経理マンを養成するための簿記入門レベルの検定試験です。
しかし、簿記3級は初めての方にとって結構高いハードルです。
一方社長にとって簿記3級が絶対必要かといいますと、社長は経理マンではないので、なくても全然構いません。
社長にとって、必要な会計知識・スキルの学び方は、
①決算書の読み方
②決算書の作り方
この順番で学ぶのがもっとも適しています。
理由は以下の通りです。
①決算書の読み方がわかると、資金の流れと利益の出る仕組みが理解できて、経営の型が理解できます。社長にはまずこれが最低限必要です。
②決算書の作り方まで学習した社長は、クラウド会計ソフトなどを使えば、期中の経理入力ができて、さらに毎月の試算表が作成できます。これによって毎月の実績が自分で作成→確認できます。
③②までマスターすると、起業初期に経理を雇う必要もなくなりますし、また税理士さんにすべて頼ることがなくなり、税理士さんとはよりレベルの高い話ができるようになることで、全体として最初から会社の経営のレベルがぐっと上がる効果があります。また、たとえ①の段階だけマスターして、②に行かなかったとしても、決算書の意味はわかるようになるので、銀行とも借入の話ができるようになります。
社長さんの中には「たかが経理・会計」と思っている方がおられるかもしれませんが、実はそうではなくて、このブログで勉強していくと、「経理・会計=経営」の図式が理解できるようになりますので、会計を勉強しようというやる気が出てくる効果があります。ぜび頑張ってついてきてくださいね。
目次
1.社長が学ぶべき会計の本当の目的
2.社長が会計を誤解する4つの理由
3.結論
1.社長が学ぶべき会計の本当の目的
そもそも会計って何のためにあるのか?
ほとんどの社長さん、特に同族企業の中小企業さんにはこのことについて、よくわかっておられません。
今このブログを読まれている社長さんも、きっとそのあたりがわからないから、このブログを読もうと思われたのだと思います。
中小企業の社長さんの多くは、会計は「税務申告のため」「銀行・取引先に見せるためにある」「会計は経理にまかせれば大丈夫」「会計は税理士にまかせれば大丈夫」などと思っておられます。
それは無理もありません。
その理由は以下を読んでいただければわかります。
しかし、現時点において、上記のような考え方でもって、社長が会社を経営しているとしたら、これは社長にとって、「致命的に間違った考え方」をしていて、これが「大きな損失」となっているのです。
もし社長さんが現時点でそう思っておられたら、ぜひ最後までじっくりこのブログを読んでください。
まず結論からお伝えします。
「会計は社長自身の会社経営のためにある」のです。
会計は経営の道具なのです。
これは私が30年以上にわたって、中小企業社長と関わってきた結論です。
もし、この時点で「なんだそんなことか」「そんな話興味ないよ」とか思われた社長はここで読むのをやめて頂いても良いです。
もし、ここまで読んでちょっとでもひっかかる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
2.社長が会計を誤解する4つの理由
では、なぜ多くの社長がこのような間違った考えになるのでしょうか?
この考えはどこから来るのかと考えたとき、以下の4つの理由によるものだと私は考えます。
①学校教育の問題
②①により財務会計、税務会計、管理会計の区別がつかない
③社長の税理士に対する間違った理解
④広告解禁による一部の税理士事務所による過剰な宣伝
4つの理由を順番に説明いたします。
①前回のブログでも書きましたが、およそ90%以上の方は簿記会計に触れることなく生涯を終えます。簿記の授業が商業高校、簿記専門学校、大学の商学部・経営学部でしかないからです。例えば高校普通科→大学(法学部・文学部・工学部・理学部・医学部・芸術学部など)のコースを専攻された方にとっては、ほぼ全く簿記に触れません。
これらの方が簿記を習うには、簿記の教科書を買って独学するか、お金を出して簿記講座を受けるしかありません。上記コースを専攻された方は自分で勉強するしかないのです。
そして簿記会計を勉強することなく会社を起業したとしたら、全く会計の基礎力ができていない恐ろしい社長が生まれるわけです。これは簿記会計をあまりにも軽視した日本教育の犠牲者です。
②①の学校教育の問題とも関連するのですが、会計はざっくり大きくわけて3つあります。
A:財務会計
B:税務会計
C:管理会計
AとBはまとめて外部報告会計(がいぶほうこくかいけい)といいます。これは決算書を会社の会社外部の利害関係者に報告するための会計です。
Cは内部報告会計(ないぶかいけい)といって、決算書を会社内部に報告する会計です。簡単にいえば、中小企業では社長および経営幹部が会社の経営を管理するためにある会計です。
実は、今このブログを読んでいただいている起業家、経営者の方の頭にある会計とはこのA、Bの外部報告会計だと思います。世間ではこれが一般的だからです。
ところで、実は私がこれから述べる、社長に身に着けてほしい会計とは、主はC:管理会計(内部報告会計)なのです。この段階でやっと社長の頭と私の頭の中が一致したかもしれません。実は会社経営に使えるのは、このC:管理会計なのです。
でも管理会計を学ぶには少なくとも、A:財務会計の知識が必要なのです。
B:の税務会計は税理士さんにお任せして大丈夫なのです。税理士さんはほとんどこの税務会計の仕事をしている方なのです。
③世間では会社を起業し、税理士さんを顧問につければ何とかなるという風潮があります。
「お金さえ払えば何とかなる」
こう思っている社長さんは多いと思います。
特に起業したての社長さんのほとんどはそう思っています。
ここで多くの社長が「会計は税務申告のためにある」と考える理由です。ここまで読まれた方はもう理解されたと思いますが、税理士さんが使っている会計は「税務会計」なのです。
税務会計とは税務申告書をつくるための会計、つまり納税するための根拠となる数字を出す会計なのです。日本の税法は「確定決算主義」といって税法にのっとった決算書を作成して、確定した利益(当期純利益)をもとにして税務申告をするという決まりになっているのです。
ところが日本の税法は世界一難解です。
税法に沿った決算書を作るには細かい税法(主に法人税法、消費税法、所得税法)の知識が必要です。
この知識と税務処理知識、スキルをもっているのが税理士さんです。
この税法に基づいた決算書作成と税務申告はざっくり言いますと、社員が50名くらいまでの会社は税理士さんにすべてお任せしているのが一般的です。ちなみにそれ以上の規模の会社になると、社内の経理責任者に実力者がおり、決算書作成+税務申告まで行うため、税理士さんの出番はあまりなくなってします。(実は私も過去ここまで全部しておりました)
今までのお話はあくまで決算の段階までの話です。「決算」というふわっとしたイメージしかもっていない方のために説明しますと、決算とは年に1回、会社で日にちを決めます。例えば社長に会社の決算日が3月31日だとしたら、その日が決算日になります。そして、社長の会社の会計期間は毎年4月1日に始まって3月31日に終わるという1年間となっているのです。会計期間は1年間、決算日は会計期間の最終日と覚えてください。
税務申告はこの決算日より2ヶ月以内、つまり3月31日が決算日でしたら2ヶ月後である5月31日が期日になります。ですので、5月31日までに決算書を完成させて、納税するための税務申告書も作成して、納税額を算定して納税する必要があるという仕組みとなっているのです。ここが税理士さんの活躍の場です。この決算書の作成と税務申告は税理士さんに任せてください。
実は会計事務所(税理士事務所)に依頼するのは、
・確定決算書作成
・納税のための税務申告書作成
のためなのです。
この2つは少なくても社員50名位になって、敏腕経理部長を雇えるようになるまでは税理士さんに任せてください。
本題に戻ります。
私がこのブログでお伝えしている「社長さんに必要なスキルとしての会計」は、ここに至るまでの4月1日から3月31日の1年間の日常の会計です。
実はここが問題なのです。
この日常の会計が、社長が学ばなければならない会計なのです。
ここはとても大事なところです。
つまり会計の基礎がない社長さんにとって税理士さんは正に「救いの神」です。自分のできないことを全部ちゃんと経理処理してくれて決算書を作ってくれて税務申告してくれる。これでOKだと、最初は思うでしょう。
しかし、それが何年かすると社長もわかってきます。
「何かおかしいな?」など。
この時点で気がついて改善した社長さんは、運がよければまだ救われます。しかし間に合わない場合もあります。ここは社長の持っている運も左右します。
なかなか難しい話なので現時点で理解できなければ、今の段階でざっくり1年間の会計処理を税理士さんにすべて丸投げすると会社経営にとって良いことはないですよ。これだけはご理解ください。
④2001年まで、税理士事務所は厳重な規制があり、広告をすることができませんでした。せいぜい看板くらいです。ところが2001年に広告解禁となりました。報酬規程も撤廃となりました。
これによって何が起こったかというと、価格競争が起こり、また一方それほどサービスの差がない税理士業務があたかも差があるような広告が出て、これが社長の会計に対する意識をさらに低下させました。
人間はどうしても楽な方に流れます。
例えば「価格が安くて、経営も指導します」なんて言ったら、そちらに流れますよね。
しかし会社設立時から「すべてをおまかせください」「しかも低価で」とか書かれると、なびいてしまいます。
しかし実態はどうでしょうか?
これに気づくには、社長に会計の知識がゼロだと何年もかかってしまいます。
実際問題として、安価で親切丁寧、経営指導までのサービスができるなんて、税理士業界の内部の事情を知っているものとしてはあり得ないのです。
しっかり経営指導しようとするとそれなりの価格になります。もちろんそのようなしっかりとした事務所もあります。でも会計を勉強したことがない社長さんには、その見分けがつかなくて、安価で宣伝の上手い税理士事務所に流れることでしょう。
結果は以下のようになります。
顧問の税理士事務所に何か不満を感じると、別の税理士事務所へとはしごをします。税理士を変えること自体は特に悪いことではありませんが、しかし社長に会計の知識がないと、次の税理士さんともまた同じ運命になってしまいます。
最近は税理士紹介会社もできていて、もちろんそれで良い税理士に出会った方もおられることでしょう。しかし、またしばらくすると不満が出てくるという方もやはりおられます。
そもそも社長に会計の知識がない状態では、良い税理士・悪い税理士を見分ける目があるはずがありません。ですからこのような社長さんはどんどん自ら袋小路に陥ってしまうのです。
3.結論
①~④で多くの社長が会計に対して抱く誤解について述べてきました。
ぜひ、今日ここまでお読みになって覚えていただきたいことをまとめますと、以下の2点です。
①会計の学習は仕訳から入るのではなく、決算書の読み方から入る。
簿記3級は経理マン養成のための入門です。
社長に必要な会計は、会社経営全体の理解から入って→次に仕訳に行くのが正しい勉強方法です。
②「会計は社長自身の会社経営のためにある」のです。会計は経営の道具なのです。
日本の簿記会計教育がごく一部の人のもののためであることから、多くの方が会計について誤った理解をしています。
会計には3種類あります。
A:財務会計
B:税務会計
C:管理会計
社長に一番必要な会計はC:管理会計ですが、管理会計を学ぶ前にA:財務会計を学ぶ必要があります。税理士さんの専門はB:税務会計です。税理士さんに任せるのは、この部分だけにするのが良いでしょう。
今日は、
①会計の学習は仕訳から入るのではなく、決算書の読み方から入る。
②「会計は社長自身の会社経営のためにある」のです。会計は経営の道具なのです。
については、しっかり覚えておいてください。
では皆さん、またお会いしましょう。